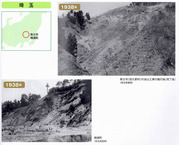2月16日の東松山市環境学習会で紹介された『全国植樹祭70周年記念写真集』(国土緑化推進機構、2019年)の巻末にある太田猛彦さんの解説「日本の森の変遷-荒廃から復活へ」(54~56頁)を読みました。全国植樹祭は1950年奈良県で「植樹行事並びに国土緑化大会」として開催され、1959年、第10回大会が埼玉県で実施されています。1970年、福島県で開かれた第21回大会から現在の名称に変更されました。全国植樹祭の前身は1934年に始まった「愛林日植樹行事」(Wikipedia)です。
日本は高温多雨の夏を持つ温帯の島国
豊かで多様な森に育まれた縄文文明
日本はユーラシア大陸の東岸に横たわる南北約3000 km の弧状列島である。しかも世界地図を広げてみればわかるように、四季が明瞭な温帯には日本のような大きな島は極めて少ない。すなわち、海の影響を受ける島々は熱帯や亜熱帯、寒帯には多いが温帯には日本列島とイギリスの2島、ニュージーランドの2島ぐらいしかない。
さらに日本列島とイギリス二島は大陸の近くに位置しその影響も受けるが、影響の受け方は全く異なり、大陸の東岸はモンスーン気候で夏季に降雨が多く、冬季は乾燥する。一方大陸の西岸は西岸海洋性気候で、夏は乾燥気味であり、冬に雨が多い。つまり日本は熱帯雨林のような高温多雨の夏を持つ世界で唯一の温帯の島国であり、そのような気候が日本の豊かな森を育んでいる。その上「冬は乾燥する 」と言っても、シベリアからの北西季節風と日本海を北上する暖流の影響で日本海側は降水量が多く、それは降雪となって日本の森林を一層多様にしている。
日本人は縄文時代の昔からそのような森に支えられた豊かな自然を利用して暮らしてきた。この時代の列島にはドングリやクリが実る落葉広葉樹の森が広がっていたため、縄文人は基本的に食糧に困ることはなく、しかも煮炊きを可能にする縄文式土器の発明によって利用できる食材の幅を広げることができたため、農耕を受け入れることがなくても豊かな生活を送ることができた。例えば 、縄文時代の遺跡として有名な三内丸山の定住集落は1700年ほど続いたと言われるが、そこでは春は山菜採り、夏は漁労、秋は木の実の採集、冬は狩猟などにより豊かな食料を得、集落の中心には木材を使った祭祀用の施設を建造していた。しかし森が大きく傷つくことはなく、自然と共生した「持続可能な社会」が展開されていたと言える。農耕の始まりを研究したジャレド・ダイアモンドは日本の縄文文明を「森を利用した最も豊かな狩猟採集民族文明」と評価している。
稲作の伝来とともに森林は劣化
江戸時代は「森林荒廃の時代」
しかし縄文時代に稲作が伝来すると、日本の森林はその後大きく変化していった。すなわち、縄文時代後期には豆類などを栽培する簡単な農業は始まり、居住地の周りの森林が変化し始めたが、水田稲作は連作は可能で、病虫害も畑作より軽微な上、何よりも単位面積当たりの収穫量が多く、したがって人口収容力も大きく、一方で用水確保のために集団生活が必要であり、集落が発達した。その結果、集落や農地の開発による森林の消失のほか、食料以外の資源は燃料も含めてほとんどが林産物であったため、いわゆる里地・里山システムを基本とする稲作農耕社会が成立するとともに集落の周りの森林の劣化も始まった。
やがて飛鳥・奈良時代以降に次々と古代都市が成立すると、建築資材等木材の本格的使用が始まって大量の木材が伐採され、畿内を中心に本来の豊かな天然林はやせ地でも育つマツ林に変わるなど森林の劣化が進行した。また、それが原因で洪水や土砂災害がたびたび発生した。そこで森林を保護するため、例えば天武天皇は676年に飛鳥川上流に禁伐令を発している。そして、10世紀末には田上山など畿内各地に荒廃山地(はげ山)が出現するようになった。
その後室町時代頃になると、各種産業の発達による人口の増加によって地方でも城郭や都市の建設が盛んになり、燃料用や資材用の木材需要が増加した。そのため森林の劣化も全国に広がっていった。またこの時代になると、製塩業、製鉄業、窯業等に必要な産業用燃料材の需要が増加して、森林の劣化がいっそう進んだ。さらに戦国時代以降、戦国大名は江戸時代の各藩によって水田の開発がいっそう進み、江戸時代中期には100万人が暮らす巨大都市江戸を要する人口3000万人の稲作農耕社会が成立した。当時の日本は世界人口の4~5%を占める人口大国であり、その人口を支えたのが稲作農業と森林を中心とする自然資源だった。しかしその頃、森林資源は既に逼迫しており、各地にはげ山が広がるとともに、里地・里山システムにかかわる入会地での村落間の境界争いや村落内での資源の奪い合い、あるいは水争いが頻発した。
一方で、森林の消失(裸地化)や劣化は山地での土砂崩壊や平地での洪水氾濫を引き起こし、それらは災害となってたびたび人々を襲った。江戸時代は「森林荒廃の時代」ということができるだろう。以降、日本の国土は20世紀前半まで、山地で土砂が生産され続け、それが河川に流出し続け、海岸に土砂を供給し続ける国土となった。幕府は土砂留工事や砂溜工事を進めるとともに、熊沢蕃山ら儒学者からの治山治水の進言を受け入れて、例えば1666年の「諸国山川掟」のような、要所での伐採禁止や植林の奨励を布告した。また幕府や各藩は今日の保安林制度につながる留山や留木の制度を制定し、海岸では飛砂害防止のために砂防林を造成した。
当時の山地・森林の様子は、例えば歌川広重の浮世絵「東海道五十三次」を見れば一目瞭然である。どの図版にも鬱蒼とした豊かな森は描かれていない。遠景の山はどの図版でも木々がまばらである一方で東海道名物の「松並木」や山腹の松が繰り返し描かれている。土壌が貧弱で他の樹木は生育できない荒れ地や砂地でもマツはよく育つ。「白砂青松」とよく言われるが、養分が少ない海岸の砂地にはマツしか生えない。つまり江戸時代の山も基本的にはこの写真集に掲載されている古い写真のような状態で、マツしか生えないほど貧弱だったのだ。
治水三法を制定した明治政府
乱伐は昭和の終戦直後まで続いた
明治時代に入ると近代産業が勃興し、人口が急増し、都市が発達したが、この時期、産業用燃料はいまだ薪炭に頼っていた。そのため、建設資材や燃料材確保の必要性から森林伐採への圧力がいっそう強まった。その結果として、明治中期は日本の森林が歴史上最も劣化・荒廃していた時期と推定される。そのため明治政府はいわゆる治水三法を制定して河川では河川法に基づく洪水氾濫防止のための連続堤工事を開始するとともに、森林法の保安林制度に基づく治山事業や砂防法に基づく砂防事業によって荒廃山地での植林を精力的に行った。しかし近代的治山治水事業が始まっても国民の大部分は依然として森林に頼る農民であり、戦争の半世紀もあって里山の荒廃地はあまり回復しなかった。この写真集の大半の写真はこの頃の里山の状況を示している。
一方、古代以来の都の造営や城郭、社寺の建設で必要な大径木は江戸時代には全国の奥山に探し求めるまでに減少したようだが、通常使われる木材もすでに江戸時代には品薄だった。そのため各地に人工林業も始まったが、大部分は天然林から伐り出された。さらに明治時代以降は近代化のための資材としての木材の需要が増大し、昭和時代に入ると森林鉄道の普及もあって奥山で本格的な伐採が始まった。加えて大戦中及び終戦直後の混乱した時代には、木材は唯一の自前の資源として文字通り乱伐された。全国植樹祭はこうした状況の中で昭和25年[1950]に始まったのである。
「拡大造林」を経て「森林飽和」へ
変わらぬ植樹活動の大切さ
以来70年。この間、奥山では列島改造~高度経済成長期に木材需要を満たすための大規模な森林伐採があり、その跡地には「拡大造林」と称してスギやヒノキ、カラマツなどが植えられた。その後外材の輸入自由化や火災防止のための木質建材の使用制限もあって国産材の需要が減少したため奥山での伐採圧力は低下した。一方里山では治山・砂防事業の成果がようやく現れ始めたのに加え、燃料や肥料が森林バイオマスから化石燃料や化学肥料に転換されて薪炭林や農用林が不要となったため森林が回復し始めた。こうして昭和時代末期から平成時代を通して日本の森林は奥山でも里山でもその蓄積を増加させ、「森林飽和」と呼べるほどに復活した。その背景には全国植樹祭を中心とした緑化運動や国民参加の森づくりによる緑化の呼びかけも大きく影響していると思われる。
一方この時代には広葉樹の復活を望む声も広がるとともに、かつての里山を保存する活動も盛んになった。この傾向は全国植樹祭の植栽樹種の選択にも表れ、1970年代からモミジやサクラ類、トチノキなど各種の広葉樹の植林が見られるようになり、1990年代に入ってからは広葉樹が大勢を占めるようになった。これは森林の全般的な成長と林業の不振の一方で1990年代以降は生物多様性保全の重要性が広く知られるようになって、多様な森づくりが好まれるようになった結果とみられる。 [以下略]
※久那村(秩父市)の治山工事施行地(完了後、1938年)(同書31頁)
※山本悟さんの「知っておきたい日本の植林史」(同書20頁)